1.乾燥概論/1-3乾燥空気について①
1-3-1乾燥しやすい条件
洗濯ものはどんなときによく乾くのでしょうか。それは、暖かくて晴れていて風が吹いている日であることは、私達は経験的に知っています。これを乾燥条件としてとらえるならば、
① 暖かい・・・・・・温度が高い(蒸発しやすい)
② 晴れている・・・・湿度が低い(水分を受取りやすい)
③ 風が吹いている・・風速が高い(水分が移動しやすい)
ということになります。

こんな日はおそらく異常乾燥注意報が出されていると思います。ですから、私達の作っている装置は強制的にこの状態を作り出して、短時間で乾燥させてやっているわけです。実際、時間をいくらかけてもよいのであればほとんどの品物の場合、天日に干しておけばよいのですが、スペースの問題や手間、異物の混入、品質管理の問題などからこういった装置が必要になるわけです。
1-3-2空気中の水分
箱型乾燥機の場合、乾燥温度については関心が払われてきましたが、乾燥機内部の湿度についてはあまり考慮の対象とはならなかったようです。医薬品の乾燥の場合、乾燥温度が50℃~70℃で、あまり高くありません。このくらいの温度で乾燥させる場合、季節による空気の状態の変化の影響を非常に受けやすく冬場と夏場では、絶対湿度が全く違うので、いくら温度を一定にしたところで、平衡水分が全く違ったものとなります。夏場になると乾燥温度を上げて生産している場合もあるようです。空調された製剤室の空気を取り入れることが可能であれば良いのですが、生産用でワンバッチ100kg程度を処理する乾燥機の場合でも、空調のバランスを崩してしまうので、外気を取り入れることが多くなります。
研究室において作られるサンプルは、空調のきいた部屋の空気を取り込んで乾燥しているので、おおむね絶対湿度は10g/kgDAです。冬場では特に晴れた寒い日などは3g/kgDA程度まで下がりますが、夏場では20g/kgDAにもなります。(図4)
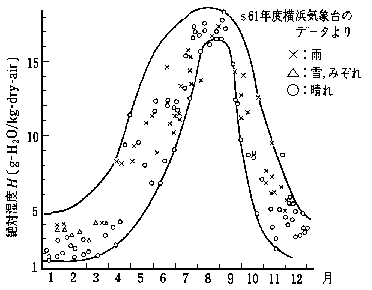
夏場でワンパス運転した空気の状態を考えると、1m×1mに広げられた粉に0.4m/sで風が通過したとすれば、24m3/分(31kg/分)の風量となり、空調された空気に対して1分間で
31kg×(20g-10g)=310gの水をスプレイした状態にしていることになります。1分間で牛乳瓶1.5本分以上の水が足された空気が粉を通過していると考えれば、乾燥状態が全く違ってくるのは、容易に想像出来ます。
1-3-3粉の中の水分
物質中の水分を分類すると、品物の粒子の表面に付着しているだけの水分と、品物の内部に吸収もしくは溶けこんでいる水分があります。前者を遊離水、後者を結晶水といいます。一般に水分測定の対象としているのは遊離水のほうです。結晶水は特別な品物を除いて、ほとんどは高温にしなければ除去出来ません。
被乾燥物の水分の表し方として、2種類の方法があります。一つは粉粒体と水分の和の全重量にたいする水分(ウェットベース WB)、もう一つは粉粒体の重量にたいする水分(ドライベース DB)があり、どちらも%で表します。

通常ウェットベースの方がよく使用されます。考え方は、濃度などと同じです。
水分(WB)= 水の重量/全重量 = 水の重量/(粉粒体の重量+水の重量)
水分(DB)= 水の重量/粉粒体の重量
水分測定は赤外線加熱式水分計を使用することが多いです。

弊社にて乾燥実験する場合、乾燥機を目的とする乾燥条件に設定し、トレイを含めた試験材料の重量を一定時間ごとに測定します。
数時間にわたり全く変化しない所を0%にし、逆算して初期水分を求めて乾燥曲線を作成します。
次項…1.乾燥概論/1-3乾燥空気について②
